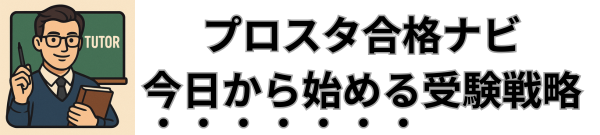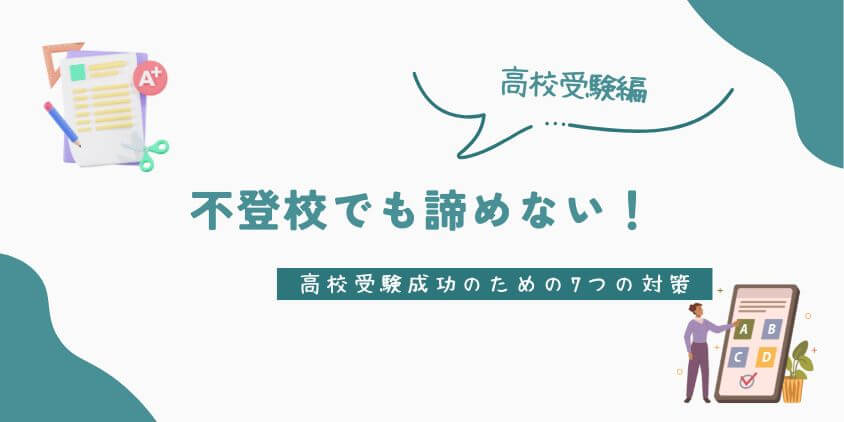「内申点や出席日数が足りなくても受験できるの?」
「子どもが受験どころか進路の話すら聞きたがらない…」
「通信制やサポート校ってどう選べばいいの?」
このような悩みを解決する記事です。
この記事を読めば、不登校の状態からでも高校受験に成功するための現実的な方法がわかります。焦らず着実に対策をとることで、お子さんの未来の選択肢は大きく広がります。
実際に、中学1年から不登校だった生徒が英検を武器に全日制高校に合格した事例や、通信制高校から大学進学を果たした体験談も紹介。保護者ができるサポートや、子どもの心に寄り添った進め方が具体的にわかります。
- 不登校からの高校受験の進め方
- 内申点や出席扱いの最新情報
- 通信制・サポート校の特徴と選び方
- 親として心がけたい接し方とメンタルケアのポイント
【対策1】焦らない!子どもと足並みを揃えることが最優先

高校受験が近づいてくると、ついつい焦ってしまいますよね。でも、ちょっと待って!
不登校からの高校受験で最も大切なのは、まず保護者と子どもの足並みをそろえることなんです。
子どもの不登校の原因がはっきりしていて、高校進学への強い意志を持っているなら話は早いですが、そんなケースはとても少ないんですよ。
「せめて高校くらいは行かせないと」という気持ちは親として当然ですが、その焦りが子どもにとってはプレッシャーになってしまうことも。
不登校になる原因は子ども自身もわからないことが多いんです。ただただ苦しい状況にいる子どもに、受験の焦りをぶつけるのはあまりにも酷。結果として状況が悪化する可能性が高いことを知っておいてください。
まずは「子どもに時間と安心を与える」ことを優先しましょう。
子どもに寄り添い話を聞く姿勢を持とう
「話をする」ということ自体が難しい場合も多いでしょう。そんな時は、安心感と時間を十分に与えてあげるだけでも十分です。
こちらの思う何倍も何倍も、安心感や時間が必要になることが多いんですよ。また、「1歩前進したら2歩下がる」ということもあるでしょう。
「わがままや甘え」が出てしまうこともあるかもしれません。それらを聞くことは本当に大変です。保護者のみなさんも生身の人間なのですから。
しかし、これらの時間は結果的に「必要な時間だった」となることが多いです。この時間を与えられた子どもほど、この先何十年もの時間を自分らしく生きることができるようになる可能性が高いのです。
タイミングを見計らって高校受験の話を始めよう
子どもの様子がある程度落ち着いたタイミングで、進路や高校受験の話を持ち出してみるとよいでしょう。
原因にもよりますが、不登校になってから1〜2カ月で多少気持ちが落ち着くケースが多いです(年単位で続くケースもあるので、あくまでもお子さんの状態・状況によります)。
時期的には、中学3年生の秋頃や、その他家庭訪問・懇談・通知表の返却などがあったタイミングがチャンスになります。早いタイミングに越したことはありませんが、くれぐれも焦らずに!
【対策2】内申点と出席日数の影響を正しく理解する

不登校からの高校受験を考える上で、避けて通れないのが「内申点」と「出席日数」の問題です。
「内申点が低いと受験できないの?」「欠席日数が多すぎて…」と心配になりますよね。でも、まずは正しく理解することから始めましょう!
内申点(調査書)とは何か?
「調査書」とは、中学校の先生が作成する「生徒の学校生活の態度と成績を書いた文書」のことです。調査書のうち、教科の成績を得点化した項目を「内申点」と言います。
一般的に、不登校だと内申点が低くなる可能性があります。その理由としては
- 学校の勉強から離れている
- 授業に出席していない
- 定期テストを受けておらず点数がない
- 定期テストを受けていても点数が低い
- 欠席日数が多い
調査書や内申点では、「中学校3年間」の生活や成績が書かれる場合もあれば、「3年生のみ」である場合もあります。出席日数のほか、英検などの資格取得や作文コンクールなどの受賞歴も記入されますよ。
調査書や内申点の付け方は、都道府県や地域によって異なりますので、お住まいの地域の基準を確認してみましょう。
出席日数が少なくても大丈夫!出席扱いになる方法がある
不登校で教室に通えなくても、出席日数を増やす方法はあるんです!
例えば:
- 保健室登校(別室登校)
- フリースクールや学習塾への「登校」
- 適応指導教室(教育支援センター)への「登校」
- オンライン教材を用いた自宅学習
保健室登校とは、その名前のとおり「学校には行くけれど、教室ではなくて保健室(別室)に登校する」ことです。利用できるかどうかは、在籍している中学校の先生に確認してみましょう。
フリースクールは不登校のお子さんが学校の代わりに通える民間の施設です。中学校の校長先生が認めれば、フリースクールや学習塾への「出席」を「学校への出席」とみなしてもらえます。
さらに、2019年に文部科学省より出された通達により、一定の条件を満たせば、自宅でのオンライン学習が出席扱いとされるようになりました。これは大きな変化で、不登校の生徒さんにとって心強い味方になりますね!
【対策3】高校選びのポイントを押さえる

不登校経験があっても、進学できる高校はたくさんあります!
でも、どんな高校を選べばいいのか迷いますよね。ここでは、不登校経験者が高校を選ぶ際のポイントをご紹介します。
全日制高校を目指す場合
一般的な高校で、不登校経験者を積極的に受け入れる学校も増えています。特に、不登校経験者向けの支援プログラムを導入している高校では、面接や作文を重視し、生徒一人ひとりの意欲や適性を評価します。
全日制を選ぶ際のポイント:
- 内申点の比重が低い入試方法がある学校を探す
- 面接重視の入試を行っている学校を検討する
- 不登校経験者への理解がある学校を選ぶ
- 少人数制や個別指導に力を入れている学校を調べる
全日制は毎日通学する必要があるため、お子さんの状態をよく見極めて判断しましょう。
通信制高校という選択肢
自宅学習を基本とする柔軟な学習スタイルが特徴です。オンライン授業を取り入れている学校も多く、時間や場所を問わず学習を進めることが可能です。
通信制高校のメリット:
- 自分のペースで学習できる
- 登校日数が少ない(月に数日程度)
- 人間関係の負担が少ない
- 多様な学習スタイルを選べる
最近の通信制高校は進学実績も上がってきており、大学進学を目指す生徒も多くいます。
サポート校という選択肢
通信制高校と連携し、個別指導や少人数授業を行う学校です。不登校経験者が安心して学べる環境を提供し、進路の選択肢を広げます。
サポート校は通信制高校の学習をサポートする民間の教育機関で、より手厚いサポートを受けられるのが特徴です。友達作りの機会も増えますし、学校行事なども通信制よりも充実していることが多いですよ。
【対策4】効果的な学習計画を立てる

不登校で学校の授業を受けられていなくても、高校受験に向けた勉強はできます!
むしろ、自分のペースで効率よく学習できるチャンスと捉えてみませんか?
基礎から始める学習計画
不登校期間が長いと、基礎的な部分から抜けてしまっていることも多いです。焦って応用問題に取り組むより、まずは基礎からしっかり固めましょう。
中学1年生の内容からわからなくなっている場合は、そこから始めることも大切です。特に数学と英語は積み上げ型の教科なので、基礎がわからないまま先に進むと、どんどん難しく感じてしまいます。
基礎学習のポイント:
- 教科書の基本例題から取り組む
- わからない単元は飛ばさず、理解できるまで取り組む
- 基礎問題集を繰り返し解く
- オンライン学習サービスを活用する
一日30分からでも構いません。コツコツと続けることが大切です。
志望校の過去問に取り組む
志望校が決まったら、その学校の過去問題を手に入れて、何度も解いてみましょう。過去問を解くことで、出題傾向がわかり、対策がしやすくなります。
過去問がなかなか手に入らない場合は、学校の先生や塾の先生に相談してみてください。多くの場合、協力してくれるはずです。
過去問学習のステップ:
- まずは時間を気にせず解いてみる
- わからない問題は解説を見て理解する
- 同じ過去問を何度も解き直す
- 本番と同じ時間配分で解く練習をする
「解けない問題ばかりで…」と落ち込むこともあるかもしれませんが、それは成長のチャンス。わからない問題こそ、重点的に対策すべきポイントなんです。
【対策5】学習サポートを上手に活用する

一人で勉強するのは大変…。そんな時は、学習をサポートしてくれる様々なサービスを活用しましょう!
不登校の生徒さんにぴったりの学習サポート方法をご紹介します。
不登校に理解のある塾や家庭教師
最近では、不登校の生徒さんに特化した塾や家庭教師サービスが増えています。こうしたサービスでは、学習面だけでなく、メンタル面のサポートも充実していることが多いです。
不登校生向け塾のメリット:
- 個別指導が基本なので、自分のペースで学べる
- 不登校経験のある講師も多く、気持ちを理解してもらいやすい
- 学校の勉強の遅れを取り戻すサポートが充実している
- 高校受験に向けた具体的なアドバイスがもらえる
家庭教師は、自宅で学べるので外出が難しい場合でも利用しやすいですね。オンライン家庭教師サービスも充実してきています。
オンライン学習サービスの活用
インターネットを活用した学習サービスも充実しています。動画授業やAI学習など、自分に合った学習方法を選べるのが魅力です。
オンライン学習のメリット:
- 24時間いつでも学習できる
- わからないところは繰り返し視聴できる
- 自分のペースで進められる
- 学習履歴が残るので、進捗状況がわかりやすい
文部科学省の方針により、一定の条件を満たすオンライン学習は出席扱いになることもあります。学校の先生に相談してみましょう。
【対策6】面接対策を万全にする

不登校経験がある場合、高校入試の面接は特に重要です。特に私立高校では、面接の比重が大きいことも多いんです。
面接で自分の思いや高校に行きたい気持ちをしっかり伝えられるよう、準備しておきましょう!
不登校について聞かれたときの答え方
面接で不登校のことを聞かれる可能性は高いです。でも、心配しないでください。大切なのは正直に、そして前向きに答えることです。
不登校について聞かれた時のポイント:
- 理由を簡潔に説明する(詳細に話す必要はない)
- 不登校期間中に学んだことや努力したことを伝える
- 高校ではどう過ごしたいかという前向きな展望を話す
- 高校に行きたい気持ちを素直に伝える
「不登校になったけど、その間に自分と向き合う時間ができて、本当に学びたいことがわかりました」といったポジティブな側面も伝えられるといいですね。
志望動機をしっかり準備する
なぜその高校を選んだのか、明確な理由を持っておくことが大切です。学校の特色や自分がやりたいことと結びつけて説明できるとベストです。
志望動機を考える際のポイント:
- 学校のホームページや学校説明会で得た情報を活用する
- その学校でしかできないことは何かを考える
- 将来の夢や目標とつなげて説明する
- 具体的なエピソードを交えると説得力が増す
「この学校は少人数制で一人ひとりを大切にしてくれると聞き、自分に合っていると思いました」など、自分の言葉で語れるようにしておきましょう。
【対策7】メンタル面のケアを忘れずに
高校受験は誰にとってもプレッシャーですが、不登校経験のある生徒さんにとっては特にそうかもしれません。
受験勉強と並行して、メンタル面のケアも大切にしましょう。
小さな成功体験を積み重ねる
大きな目標だけを見ていると、プレッシャーに押しつぶされそうになることも。まずは小さな目標を設定して、達成感を味わうことから始めましょう。
例えば:
- 今日は30分勉強する
- 英単語を10個覚える
- 数学の基本問題を3問解く
こうした小さな成功体験が自信につながり、「やればできる」という気持ちを育てます。
リラックス法を身につける
勉強で疲れたり、不安になったりしたときのリラックス法を持っておくと安心です。
おすすめのリラックス法:
- 深呼吸(4秒吸って、6秒かけて吐く)
- 好きな音楽を聴く
- 軽い運動や散歩をする
- 入浴でリラックスする
無理をせず、休息も大切にしながら受験勉強を進めていきましょう。
周囲のサポートを受け入れる
一人で抱え込まず、家族や先生、カウンセラーなど、周囲のサポートを受け入れることも大切です。
つらいときは「助けて」と言える勇気を持ちましょう。それは弱さではなく、前に進むための強さです。
不登校経験のある先輩の体験談を聞くことも、大きな励みになりますよ。「自分だけじゃない」という気持ちが、心強さにつながります。
不登校からの高校受験成功事例
不登校から高校受験に成功した実例をご紹介します。これらの事例が、あなたやお子さんの希望になれば嬉しいです。
中1から不登校、全日制高校に合格したAさんの場合
Aさんは中学1年生の3学期から学校に行けなくなりました。原因は人間関係のトラブルでした。
最初は勉強のことなど考えられない状態でしたが、少しずつ気持ちが落ち着いてきた中学3年生の夏頃から、家庭教師を週2回お願いすることにしました。
基礎からコツコツと学習を進め、特に得意だった英語に力を入れて英検3級も取得。内申点は低かったものの、私立高校の面接で自分の思いをしっかり伝え、英語の試験でも良い点数を取ることができました。
今では高校生活にも慣れ、英語部で活躍しているそうです。
中2から不登校、通信制高校から大学進学を果たしたBさんの場合
Bさんは中学2年生から不登校になりました。学校の勉強についていけず、次第に登校することが苦痛になったといいます。
中学3年生になって進路を考えたとき、毎日学校に通うのはまだ難しいと感じ、通信制高校への進学を決意。
通信制高校では自分のペースで学習を進められることに安心感を覚え、徐々に自信を取り戻していきました。高校2年生からはサポート校にも通い始め、大学受験の準備も開始。
見事、希望の大学に合格し、今では将来の夢に向かって勉強を続けています。
「不登校だった経験があったからこそ、自分と向き合う時間ができた。それが今の自分につながっている」とBさんは話しています。
まとめ:不登校でも諦めない!高校受験成功のために
不登校だからといって、高校進学を諦める必要はありません。むしろ、自分に合った学び方や進路を見つけるチャンスと捉えることもできます。
この記事でご紹介した7つの対策を参考に、ぜひ高校受験に向けて一歩ずつ進んでいってください。
- 【対策1】焦らない!子どもと足並みを揃えることが最優先
- 【対策2】内申点と出席日数の影響を正しく理解する
- 【対策3】高校選びのポイントを押さえる
- 【対策4】効果的な学習計画を立てる
- 【対策5】学習サポートを上手に活用する
- 【対策6】面接対策を万全にする
- 【対策7】メンタル面のケアを忘れずに
不登校は決して恥ずかしいことではありません。一人一人に合った学び方や生き方があります。
「うちの子、大丈夫かな…」と不安になることもあるでしょう。でも、あなたのお子さんには無限の可能性があります。
焦らず、お子さんのペースを尊重しながら、一緒に前に進んでいきましょう。きっと素敵な高校生活が待っていますよ!
あなたとお子さんの未来が明るいものになりますように。