「中学受験の勉強に集中したいけど、英語の勉強も続けるべき?」
「志望校に英語入試がないけど、英語学習は無駄にならない?」
「英検対策って本当に中学受験に役立つの?」
このような悩みを解決する記事です。
中学受験と英語学習をどう両立させるべきか、今後の教育環境を見据えた効率的な学習戦略を具体的に紹介します。
筆者自身や多くの家庭で、英語を“やめずに続けた”ことで受験にもその後の学習にも好影響があった事例も取り上げています。
この方法で問題が解決できた、という声や「中学受験後にも通用する英語力を身につけられた」といったメリットも豊富に紹介。
- 中学受験における英語入試の最新動向
英語学習を続けるべき理由と最適なタイミング
学年別・効率的な英語学習法
英語学習を一時中断すべきケースの判断基準
中学受験における英語入試の現状
まず、中学受験における英語入試の現状について見ていきましょう。実は、英語を入試科目に取り入れる学校が年々増加しているんです。
2024年度のデータによると、首都圏では142校、関西圏では70校の学校が英語入試を導入しています。この数字は今後も増えていくと予想されています。
 関西圏でも、大阪薫英女学院、金蘭会、武庫川女子大学附属、京都光華、立命館守山などが英語入試を導入しています。これらの学校では、グローバルな視野を持つ生徒を育てるために、入試科目に英語を追加しているのです。
関西圏でも、大阪薫英女学院、金蘭会、武庫川女子大学附属、京都光華、立命館守山などが英語入試を導入しています。これらの学校では、グローバルな視野を持つ生徒を育てるために、入試科目に英語を追加しているのです。
英語入試の形式は学校によって異なります。例えば、国語・算数・英語の3科目から2科目を選択する形式や、英語だけで受験できる学校もあります。中には英検などの外部検定を活用した優遇制度を設けている学校もあるんですよ。
英語入試が増えている理由
なぜ英語入試を導入する学校が増えているのでしょうか?主な理由は以下の2つです。
1つ目は、小学校における英語教育の変化です。2020年から小学校での英語が本格的に授業に組み込まれました。特に、3・4年生は英語が「必修化」され、5・6年生では国語や算数と同等に「教科化」されたのです。
このような教育改革により、小学生でもある程度の英語力が求められるようになりました。
2つ目は、グローバル人材育成の必要性です。世界で活躍するために必要不可欠な英語力を持つ人材を育てるため、英語を入試科目に加える学校が増加しています。
英語を中学受験に取り入れることで、小学生のうちから英語に興味を持っている生徒を確保し、グローバルな視野を持った生徒を育成できると考えられているのです。
中学受験の英語入試ではどんな問題が出るの?
中学受験における英語入試の出題形式は、学校によって大きく異なります。筆記試験だけでなく、面接やリスニングを組み合わせる学校もあり、多様化が進んでいます。
筆記試験
筆記試験では、語彙や文法、英作文など基本的な英語力を問う問題が出題されます。一般的には、小学校の学習内容をベースにした問題が多いですが、学校によってはそれを超えたレベルの英語力が求められることもあります。
 特に英作文の問題では、与えられたテーマについて自分の意見を英語で表現する力が試されます。例えば、「自分の好きな本について英語で紹介しなさい」といったテーマが出題されることがあります。
特に英作文の問題では、与えられたテーマについて自分の意見を英語で表現する力が試されます。例えば、「自分の好きな本について英語で紹介しなさい」といったテーマが出題されることがあります。
リスニング
リスニング試験では、英語の音声を聞いて内容を理解する力が問われます。簡単な会話や短い文章を聞いて、質問に答える形式が一般的です。
リスニング問題は、日常会話レベルの内容から、学校生活や趣味に関する話題まで幅広く出題されます。英語の音に慣れていることが重要なポイントになります。
面接
面接試験を実施する学校では、簡単な自己紹介や質疑応答を英語で行うことが求められます。英語でのコミュニケーション能力を見るための試験です。
面接では、「名前」「好きな科目」「趣味」など基本的な質問から、「将来の夢」「なぜこの学校を志望したのか」といった少し複雑な質問まで出されることがあります。
中学受験の英語入試で求められるレベルは?
中学受験の英語入試で求められるレベルは、学校によって異なりますが、一般的には英検でいうとどのレベルが目安になるのでしょうか?
 多くの学校では、英検5級〜3級程度のレベルが求められます。特に難関校では英検準2級、あるいは2級レベルの問題が出題されることもあります。
多くの学校では、英検5級〜3級程度のレベルが求められます。特に難関校では英検準2級、あるいは2級レベルの問題が出題されることもあります。
学年別に目標となる英検レベルを見てみましょう。
- 小4:英検5級〜4級(英語に慣れる段階)
- 小5:英検4級〜3級(自信とモチベーションにつながる)
- 小6:英検3級〜2級(出願・加点目的での受験も視野に)
英検の資格を持っていると優遇措置を受けられる学校も増えています。例えば、三田国際学園では英検準1級以上、TOEFL iBT 72点以上、IELTS 5.5以上を保有している場合は英語筆記試験が免除されます。
また、森村学園中等部では英検3級以上で入試加点、大妻中野中学校では英検2級以上で試験免除といった制度があります。
慶應義塾湘南藤沢中等部では、英検は入試制度の優遇にはなりませんが、英語の試験レベルとしては英検2級から準1級程度の問題が出題されるため、しっかりとした英語対策が必要です。
中学受験と英語学習、両立させるべき?それとも後回し?
ここからが本題です。中学受験を控えたお子さんの英語学習は続けるべきか、それとも一時中断して受験勉強に集中すべきか。多くの保護者が悩むポイントですよね。
結論から言うと、可能であれば両立させることをおすすめします。その理由をご説明しましょう。
 小学校時代は「英語習得の黄金期」
小学校時代は「英語習得の黄金期」
小学校時代は「英語習得の黄金期」と言われています。日本語の読解力が著しく発達するこの時期は、英語力も伸び盛りなのです。
バイリンガル研究の世界では、日本語も英語も、言葉の力は底辺で繋がっている(氷山説)が定説となっています。つまり日本語の運用能力が発達する小学校時代は、英語力も同じように伸ばしやすい時期なのです。
子どもの成長を長期的視野で考えた時、小学校時代は「英語の読解力」を強化する時期と言えます。英語は他の教科と違っていくらでも「先取り」ができるのも特徴です。
10歳までが言語習得の最適期
ボストン大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学の研究チームによる調査では、ネイティブレベルの高度な英語力を身につけるには「10歳まで」に英語学習をスタートする必要があることがわかっています。
10歳以降に英語学習をスタートした場合、ネイティブレベルの英語力を身につけるのは極めて難しいというデータが示されています。
これは10歳を過ぎると英語が身につかないという意味ではなく、10歳までが最適期だということです。言語吸収力が高い10歳までに英語の基礎力を構築しておくことが、子どもにとって最も学習負担が少なく、また、「一生使える英語力」を獲得しやすいのです。
中学受験と英語学習を効率的に両立させる方法

では、中学受験と英語学習を効率的に両立させるにはどうすればよいのでしょうか?具体的な方法をご紹介します。
学年別の英語学習戦略
学年に応じた英語学習の取り組み方を考えましょう。
この時期は英語に楽しく触れることが大切です。英語の歌やアニメ、絵本などを通して、英語の音やリズムに慣れさせましょう。無理なく続けられる範囲で、英語への興味を育てることが目標です。
基本的な単語や簡単なフレーズを覚え始める時期です。英検5級や4級にチャレンジするのもよいでしょう。この時期から中学受験の勉強も始まりますが、週1〜2回程度の英語学習は続けることをおすすめします。
中学受験の勉強が本格化する時期です。英語学習の時間は限られてきますが、週1回程度は継続することで、これまで培ってきた英語力を維持できます。英検3級の取得を目指すのもよいでしょう。
受験勉強が最も忙しくなる時期ですが、志望校が英語入試や英検による優遇制度を設けている場合は、それに合わせた対策を行いましょう。英検3級や準2級の取得が、受験に有利に働くこともあります。
時間の効率的な使い方
限られた時間の中で、中学受験の勉強と英語学習を両立させるには、効率的な時間の使い方が重要です。
- 朝の時間を活用する
- 朝は頭がすっきりしている時間帯です。朝の10〜15分間を使って、英単語の復習や簡単なリスニング練習を行うのも効果的です。
- 移動時間を活用する
- 塾への移動時間や待ち時間を利用して、英語の音声教材を聴くことで、リスニング力を維持できます。
- 英語学習日を固定する
- 週に1〜2日、英語学習の日を決めておくと、習慣化しやすくなります。例えば、「土曜日の午前中は英語の時間」というように決めておくと、継続しやすくなります。
オンライン英語学習の活用
最近では、中学受験と英語学習を両立させるためのオンライン英語学習サービスも充実しています。これらのサービスは、時間の制約がある中でも効率的に英語を学べるよう設計されています。
無理なく継続可能な時間設計や、子どもの性格・レベルに合わせた個別指導、英検対策コースなど、受験と直結した学びができるサービスもあります。
英語学習を一時中断するべきケース
一方で、英語学習を一時中断した方がよいケースもあります。どんな場合に英語を後回しにすべきか、考えてみましょう。
お子さんが受験勉強で精神的・時間的に余裕がない場合は、英語学習を一時中断することも選択肢の一つです。特に受験直前の小6の秋以降は、受験科目に集中した方が効果的な場合もあります。
ただし、完全に英語から離れてしまうと、これまで培ってきた英語力が低下してしまう可能性があります。可能であれば、週に1回15分程度でも英語に触れる時間を作ることをおすすめします。
英語より優先すべき課題がある場合
受験科目(国語・算数・理科・社会)に苦手科目があり、その克服が急務である場合は、一時的に英語学習を中断し、苦手科目の対策に時間を使うことも検討すべきでしょう。
特に算数や国語は、他の科目の土台となる重要科目です。これらの基礎がしっかりしていないと、他の科目の学習にも影響します。まずは受験に必須の科目の基礎固めを優先させることも大切です。
志望校の入試に英語が関係ない場合
志望校の入試に英語が全く関係なく、英検などの資格も評価されない場合は、受験直前期(小6の秋以降)は英語学習を一時中断することも選択肢となります。
ただし、前述したように小学生時代は言語習得の黄金期です。中学受験後の英語学習を見据えて、可能な範囲で英語に触れる機会を残しておくことをおすすめします。
まとめ:お子さんの将来を見据えた選択を
中学受験と英語学習の両立について、さまざまな観点から見てきました。最後に、ポイントをまとめておきましょう。
- 中学受験における英語入試は年々増加傾向にあり、英検などの外部検定を活用した優遇制度を設ける学校も増えています。
- 小学校時代は「英語習得の黄金期」であり、特に10歳までが言語習得の最適期とされています。
- 可能であれば中学受験と英語学習を両立させることが理想的ですが、お子さんの状況や志望校の特性に応じて柔軟に対応することが大切です。
- 効率的な時間の使い方やオンライン英語学習の活用など、両立のための工夫も多くあります。
- 受験勉強で手一杯の場合や、英語より優先すべき課題がある場合は、一時的に英語学習を中断することも選択肢の一つです。
最終的には、お子さんの性格や学習スタイル、志望校の特性、そして将来の目標に合わせて、最適な選択をすることが大切です。
中学受験は通過点であり、その先の長い人生を見据えた選択をすることが重要です。お子さんの将来にとって何が最善かを考え、バランスの取れた学習計画を立てていきましょう。
どうですか?中学受験と英語学習の両立について、少し見通しが立ちましたか?お子さんの可能性を最大限に引き出すために、ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。
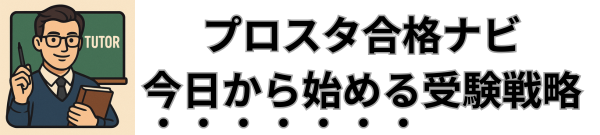
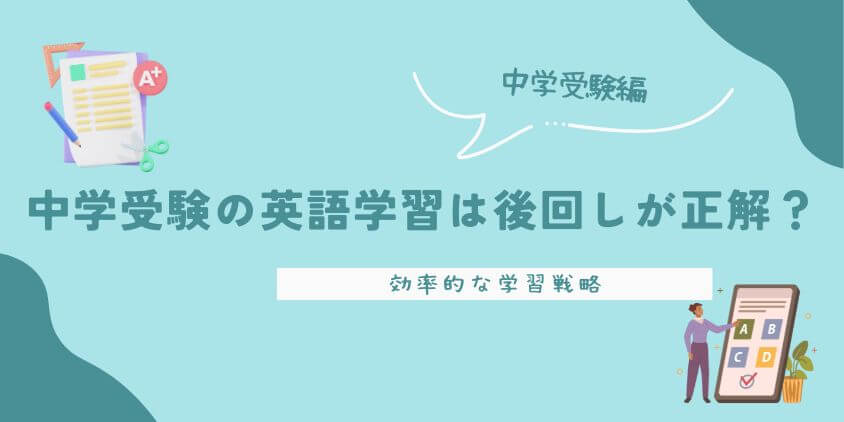
 小学校時代は「英語習得の黄金期」
小学校時代は「英語習得の黄金期」