「同じ偏差値なのに、模試によって判定が全然違うのはなぜ?」
「どの模試を受ければ、志望校合格に近づけるの?」
「模試の結果ってどう読み取って、どう活かせばいいの?」
このような悩みを解決する記事です。
四大模試(SAPIX・四谷大塚・日能研・首都圏模試)の違いを徹底比較し、偏差値の読み方や模試の選び方、活用法までわかりやすく解説します。
受験経験者の体験談も交えて、実際に「模試をうまく使って合格につなげた」方法をご紹介!
- 四大模試の特徴と偏差値の違い
- 志望校に応じた模試の選び方
- 模試結果の正しい読み方と活用法
- 公立中高一貫校向け模試の特徴
この記事でわかること
四大模試の特徴と偏差値の違い
志望校に応じた模試の選び方
模試結果の正しい読み方と活用法
公立中高一貫校向け模試の特徴
四大模試とは?それぞれの特徴と偏差値の違い

中学受験の世界では「四大模試」と呼ばれる大規模な模擬試験があります。これらは受験者数が多く、長年の実績があるため、志望校判定の精度が高いとされています。
でも、同じ「偏差値」という言葉を使っていても、模試によって数値の意味がまったく違うんです。これを知らないと、お子さんの実力を見誤ってしまうことも…。
それでは、四大模試それぞれの特徴と偏差値の違いを見ていきましょう。
1. サピックス(SAPIX)の模試
サピックスの模試は、最難関校を目指す受験生向けの模試として知られています。
最大の特徴は「受験者層のレベルが高い」「問題の難易度が高い」という点です。サピックスやグノーブルなど、最難関校への合格実績が豊富な塾の生徒が受験するため、最難関校への合格可能性を測る模試としては精度が高いと言えます。
ただし、問題の難易度が非常に高く、受験者の学力レベルも高いため、偏差値が他の模試よりも低めに出る傾向があります。
 サピックスオープンの6年生の主な模試には、志望校判定サピックスオープン(6年生4月〜7月)、合格力判定サピックスオープン(6年生9月〜12月)、学校別サピックスオープン(難関校別の専用模試)などがあります。
サピックスオープンの6年生の主な模試には、志望校判定サピックスオープン(6年生4月〜7月)、合格力判定サピックスオープン(6年生9月〜12月)、学校別サピックスオープン(難関校別の専用模試)などがあります。
学校別サピックスオープンは、特定の難関校の入試傾向に特化した問題が出題されるため、志望校対策としても非常に有効です。
2. 四谷大塚の模試
四谷大塚は、もともとテスト会として発足した塾であり、テストに関しては長い歴史と豊富なデータを持っています。
四谷大塚の「合不合判定テスト」は、かつては難関校の判定には欠かせないテストとして多くの受験生を集めていました。40年以上の歴史を持ち、首都圏随一の合否判定テストとして知られています。
ただし、出題傾向に「四谷大塚流」とでも言いたくなる独特の癖があり、日頃から四谷大塚(あるいは提携塾)に通って日曜テストを受けている生徒が有利になる傾向があります。
また、四谷大塚は男女別の母集団で偏差値をつけているため、女子では日能研と比べて四谷大塚の偏差値が1〜2程度高めに出る傾向があります。
3. 日能研の模試
日能研の模試は、テストの種類が多く、ネーミングも似通っているためわかりづらい面がありますが、主に「合格判定テスト」が四谷大塚の「合不合判定テスト」に相当するテストです。
6年生になると、毎月どれかのテストがあり、9月以降は月に2〜3本、そして12月には5本ものテストがあるというスケジュールになっています。
問題の特徴としては、癖のあるテストではなく、よく言えば無難、悪く言えば特徴が薄いという印象です。難易度は少し低めで、中堅校〜難関校の志望校判定に適しています。
 4. 首都圏模試(首都圏模試センター)の模試
4. 首都圏模試(首都圏模試センター)の模試
首都圏模試センターの模試は、大手中学受験塾ではなく、模擬試験を専門にしている会社が運営しています。
最大の特徴は「母集団のレベルがやや低め」という点です。そのため、中堅下位校の志望校判定に適しているとされています。
また、首都圏模試は日能研に対して9程度高めに出るというイメージがあります。つまり、同じ学力レベルでも、首都圏模試では偏差値が高く出る傾向があるのです。
自宅受験が可能という点も大きな特徴で、地方在住者や塾に通っていない受験生にも人気があります。
四大模試の偏差値比較表
同じ学校でも、模試によって偏差値がこれだけ違います!例えば、男子校の本郷(2月1日・第1回入試)の合格率80%ラインとなる偏差値は次の通りです(2020年度のデータ):
- 四谷大塚:偏差値59
- 日能研:偏差値58
- SAPIX:偏差値49
- 首都圏模試センター:偏差値69
同じ学校なのに、SAPIXと首都圏模試では20もの開きがあるんです!
これだけ違いがあるので、異なる模試の偏差値を単純に比較することはできません。各模試の特性を理解した上で、お子さんの実力を判断することが大切です。
模試の選び方と受験タイミング
「どの模試を受ければいいの?」「いつから受け始めるべき?」という疑問にお答えします。
基本的には、お子さんが通っている塾の模試をメインに受験することになりますが、志望校のレベルや特性によって、他の模試も併用するとより精度の高い判定が得られます。
志望校のランク別におすすめの模試を紹介すると:
- 難関校〜最難関:SAPIX
- 中堅校〜難関校:日能研・四谷大塚
- 下位校〜中堅校:首都圏模試
ただし、これはあくまで目安です。例えば、早慶の付属校などは難解な設問が少ないため、難関校であってもサピックス模試が良いとは限りません。その場合、四谷大塚や日能研、あるいはクセのない出題が多い首都圏模試を受けてみるのも良いでしょう。
受験タイミングについては、小4、小5の段階では、模試の目的は同学年における相対的な学力評価や弱点の認識です。小6になると、志望校の合格判定に応じて受験校の検討が必要になります。
小6の場合、四大模試はそれぞれ次のようなスケジュールで実施されています:
- サピックス:志望校判定(4月〜7月)、合格力判定(9月〜12月)、学校別(随時)
- 四谷大塚:合不合判定テスト(4月〜12月で6回)
- 日能研:各種テスト(毎月、9月以降は月2〜3回、12月は5回)
- 首都圏模試:合判模試(4月、7月、9月、10月、11月、12月)
どうですか?模試がこんなにたくさんあるなんて、知らなかった方も多いのではないでしょうか。
でも、すべての模試を受ける必要はありません。志望校のレベルや特性に合わせて、効果的な模試を選ぶことが大切です。
模試結果の正しい読み方と活用法
模試の結果表を前に「この数字、どう読めばいいの?」と悩んでいませんか?
模試の結果を正しく読み解き、効果的に活用するためのポイントをご紹介します。
1. 偏差値(順位)と志望校合格判定
偏差値は、その模試を受けた集団の中での相対的な位置を示すものです。しかし、前述したように模試によって大きく異なるため、単純に数値だけを見て一喜一憂するのはおすすめできません。
大切なのは、その塾(およびその模試の受験者)から志望校に何人くらいの合格者が出ているのかを調べ、塾の先生にどのくらいの偏差値を取っているとどれくらい合格可能性があるのかを聞いておくことです。
例えば、女子の四大模試の結果偏差値2025(理系サラリーマンの投資と中学受験伴走ブログより)を見ると、同じ学校でも塾によって偏差値が上下していることがわかります。
豊島岡、早実、市川、洗足①、明大明治①、吉祥女子①など、ある塾で上がってある塾では下がっているという学校が多く、複数の模試で方向が揃ったのは、青学の上げ、筑附と白百合の下げくらいだそうです。
また、フェリスのN偏差値(日能研)は2017年以来ずっと62でしたが、2025年は61に下がったとのこと。日能研は伝統的にフェリスに強く、塾別の合格者数は2年連続でSAPIXを抑えて1位だそうです。
 2. 弱点の洗い出しと対策
2. 弱点の洗い出しと対策
模試の結果は、お子さんの弱点を発見し、対策を立てるための貴重な情報源です。
科目別、単元別の正答率や、間違えた問題の傾向を分析することで、効率的な学習計画を立てることができます。
特に、複数回の模試で同じ単元が苦手という結果が出ている場合は、重点的に対策する必要があります。
わが家の場合、息子が算数の図形問題で毎回点数を落としていることがわかり、図形に特化した問題集を追加したところ、次の模試では大幅に成績が上がりました!
3. テストの受け方の見直し
模試は、本番の入試と同じような環境で行われるため、時間配分や解答の仕方など、テストの受け方を見直す良い機会です。
例えば、時間が足りずに最後まで解けなかった、見直す時間がなかったなどの問題があれば、時間配分の練習が必要かもしれません。
また、マークシートの塗り方や、記述問題の書き方なども、模試を通じて練習することができます。
4. 志望校の再検討
6年生の模試においては、志望校の合格判定が重要になります。
受験本番はチャレンジングな難関校だけでなく、安全校も受験する必要がありますので、それらをバランスよく検討するための材料として模試の結果が必要になります。
模試を受ける度に大きく成績が上下するのであれば、それに応じて、模試の際に記入する志望校も調整しなければいけません。入試日程も考慮した上で、チャレンジ校、安全校をバランスよく選びましょう。
公立中高一貫校志望者向けの模試情報
近年人気の公立中高一貫校を目指している方向けの情報もお伝えします。
公立中高一貫校は、私立中学とは異なり「適性検査」という独自の入試形式を採用しています。そのため、対策も私立中学受験とは異なります。
公立中高一貫校向けの模試としては、以下のようなものがあります:
- 四谷大塚:公立中高一貫校対策実力判定テスト(6年生の秋に2回)
- 日能研:公立中高一貫校対策の各種テスト
- 首都圏模試:適性検査型模試(7月、9月、11月)
サピックスには公立中高一貫校向けの専門模試はありません。
 四谷大塚は公立中高一貫校対策に強みを持つ塾ではないので、あえてこのテストを受ける必要はないかもしれません。会員の生徒にとっては有効です。
四谷大塚は公立中高一貫校対策に強みを持つ塾ではないので、あえてこのテストを受ける必要はないかもしれません。会員の生徒にとっては有効です。
公立中高一貫校の適性検査は、知識を問うというよりも、思考力や表現力を問う問題が多いのが特徴です。そのため、模試でも単なる知識の確認ではなく、思考力や表現力を試す問題が出題されます。
適性検査型の模試を受けることで、本番の雰囲気に慣れるとともに、自分の思考力や表現力のレベルを確認することができます。
特に記述問題の対策は重要で、模試の添削結果を参考に、どのような記述が求められているのかを理解することが大切です。
まとめ:模試を味方につけて志望校合格を目指そう
ここまで、中学受験における四大模試の特徴と偏差値の違い、模試の選び方と受験タイミング、結果の読み方と活用法について解説してきました。
最後に、模試を効果的に活用するためのポイントをまとめておきます:
- 四大模試(サピックス、四谷大塚、日能研、首都圏模試)はそれぞれ特徴が異なり、偏差値の出方も大きく違うことを理解する
- 志望校のレベルや特性に合わせて、適切な模試を選ぶ
- 模試の結果は、単なる順位や偏差値だけでなく、弱点の発見や対策、テストの受け方の改善、志望校の再検討など、多角的に活用する
- 公立中高一貫校志望者は、適性検査型の模試を活用して思考力や表現力を鍛える
模試の結果に一喜一憂するのではなく、模試を味方につけて志望校合格を目指しましょう!
お子さんの成長を長い目で見守りながら、適切なサポートをしていくことが大切です。模試はあくまでも道具の一つ。最終的には本番の入試で実力を発揮できるよう、バランスの取れた学習を心がけましょう。
中学受験は親子で乗り越える大きな山。この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです!
みなさんの受験が実り多きものになりますように!
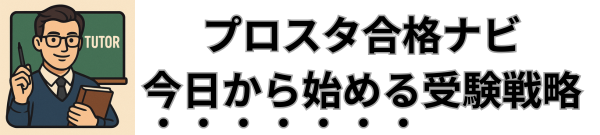
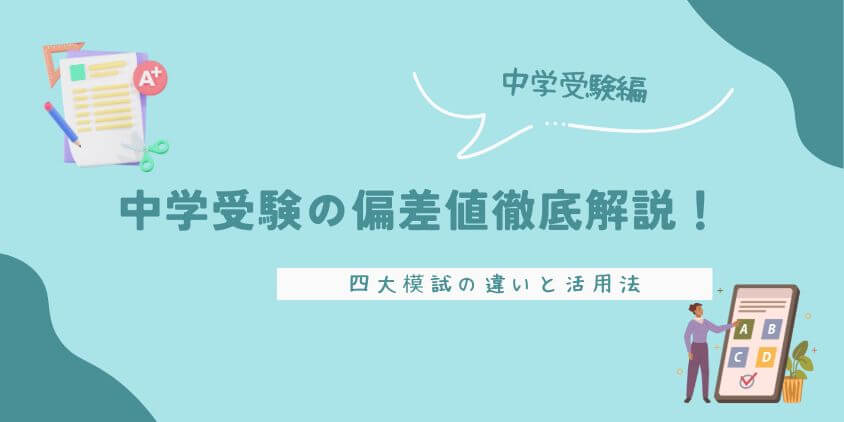
 4. 首都圏模試(首都圏模試センター)の模試
4. 首都圏模試(首都圏模試センター)の模試